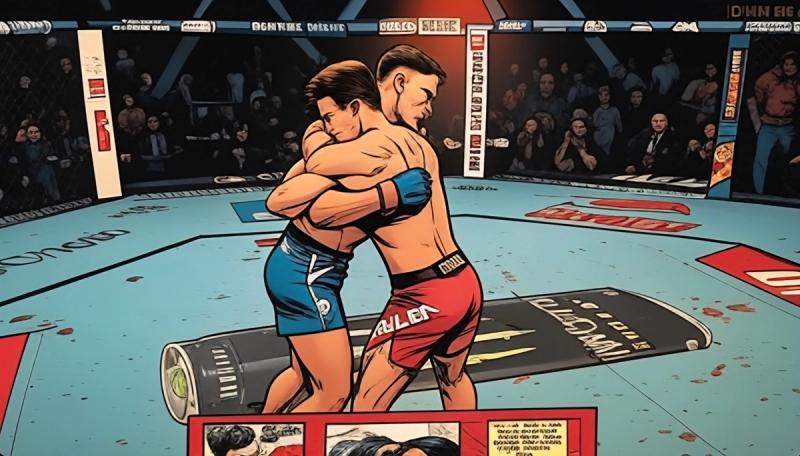私たち格ヲタは皆、血湧き肉躍るドラマを求めて格闘技を観ます。
KO決着の瞬間、会場が一体となるあの熱狂。鋭いジャブ、華麗なハイキック、そして失神KO――。
格闘技の「華」といえば、やはりスタンドでの打撃戦に他なりません。
しかし、多くのMMAファンにとって、ある種の「沈黙の時間」があるのではないでしょうか。
それは、選手たちが組み合い、グラウンドにもつれ込んだ瞬間です。
「何をやってるんだ?」「膠着じゃないのか?」「レフリー、早くブレイクしろ!」
正直なところ、私もそう思っていました。
私は父の影響でPRIDE育ち、大晦日に紅白歌合戦を見ない家庭で育ちました。
もちろんその頃は、ヒョードル、ミルコ、ノゲイラが鎬を削るヘビー級戦国時代。
派手な打撃で相手をブッ倒すことこそが正義だと思い込んでいました。
軽量級やグラップラーによる「こちゃこちゃした」ファイトは正直意味不明でした。組み付いたのを見たら「さっさと離れて殴り合え!」とさえ思っていたのです。
もし、かつての私のように感じている方がいるなら、はっきりと言います。
その「謎の時間」こそ、MMAの真の深淵であり、最高の知的な攻防が繰り広げられている瞬間です。
そして、この深淵を覗き込む方法はただ一つ。柔術、あるいはグラップリングをほんの少しでも体験してみることです。
断言します!寝技を学ぶと、あなたのMMA観戦は(最低でも3倍!)おもしろくなります。
寝技が分かると「見え方」が変わる
1. 「謎の時間」が「考える時間」に変わる
なぜ寝技が分かりにくいのか?
それは、寝技の攻防が瞬間的な破壊ではなく、段階的な論理で構成されているからです。打撃が一発で終わるのに対し、寝技は「次の攻撃のための準備」の連続です。
この論理を理解するためのキーワードが「ポジション」です。
柔術やグラップリングでは、まず相手を仕留めることより、「自分が優位な位置(ポジション)を確保し、相手にダメージやリスクを与える位置を奪うこと」が最優先されます。
例えば、以下のポジションです。
マウントポジション
相手にのしかかり、打撃を打ち込める究極の優位な位置。上の相手が優位なのは素人目にも一目瞭然。
バックポジション
相手の後ろに張り付き、チョークスリーパーを狙う位置。これもバックキープしている方が優位なのはわかりますよね。
ガードポジション: 下になりながらも、足を駆使して防御し、関節技やスイープ(体勢をひっくり返すこと)を狙う防御兼攻撃の位置。
一見どっちが何を狙っているのかわからないですが、このポジションの攻防もかなりおもしろい!
寝技の攻防が始まっても、多くのファンは「どっちが優勢なの?」と疑問に思うでしょう。しかし、これらのポジションの優劣が分かると、俄然、試合がクリアに見えてきます。
選手が少しも動かないとき、それは「膠着」ではなく、「どう動いても良い位置(打撃や関節技を狙える位置)を取りたい」選手と、「その位置を取らせまいとする」選手の、まさに静かで激しい「綱引き」の時間なのです。
寝技を学ぶと、この「綱引き」の意図が手に取るように分かるようになります。
2. 「仕掛け」と「防御」の論理が理解できる
打撃技は「一発の爆発力」ですが、寝技は「関節技・絞め技への布石(セットアップ)」の連続です。
寝技を体験すると、「ああ、ここで相手の腕をクラッチ(ロック)したのは、あの三角絞めのセットアップなんだ!」とか、「この選手はハーフガードからディープハーフに潜り込むのが得意なんだな」といった、個々の選手の戦略が浮き彫りになってきます。
動きが少ないように見えても、彼らは数分先の未来を見据えて「手の置き場」「腰の切り方」「呼吸のコントロール」といった、微細な情報戦を行っているのです。この「静かな知恵比べ」の裏側を知ることで、あなたは真のMMAの奥深さを知ることになります。
寝技経験者が語る「共感」の楽しさ
1. 選手の「すごさ」が次元を変えて伝わってくる
私が寝技を始めて本当に良かったと感じるのは、「重圧」の再現性を実感できたことです。
マウントポジションやサイドポジションで、体格の近い相手に「乗られる重さ」を体験すると、その重圧たるや、全身の自由を奪われるような窒息感です。
そして、トップMMAファイターたちが、その尋常ではない重圧の中で、一瞬の隙を突いて体を入れ替え、ポジションを逆転させる姿を見たとき、鳥肌が立ちました。
「あの状況で動けるなんて、人間じゃない」
これは、ただ見ていた頃には決して分からなかった、フィジカルと技術が複合した凄みです。寝技を学ぶことで、観戦中に感じる興奮が、ただの「派手さ」ではなく、「技術と力の極限のぶつかり合い」という、より専門的で深みのあるものに変わるのです。
2. 「私の格闘技」としてMMAが楽しめる
スタンドの攻防は、生まれ持った身体能力や天性の「打撃センス」に左右される部分が大きく、なかなか自分事として捉えにくいかもしれません。
しかし、柔術・グラップリングは違います。
寝技は「柔よく剛を制す」という言葉が表すように、体格や力に劣る者が、「梃子の原理」や「骨格の仕組み」という論理を用いて、大男をひっくり返すことが可能です。
これは、あなたがジムで体験した「一本取れた喜び」や「この体勢から抜け出せない苦しさ」と完全にリンクします。
観戦中に、選手が繰り出す技に対し、「あ!これ、この前道場で練習したやつだ」「この体勢、どうやって防いだらいいんだろう?」と、自分自身の経験を重ね合わせるようになるのです。
MMA観戦は、単なる他人の試合ではなく、「自身の知識と経験を試す場」へと昇華します。いまでは寝技の攻防が本当に楽しく、軽量級の試合でさえ、一瞬も目が離せなくなりました。
3. 柔術をやっていなかったらスルー」していた試合
最近、私が柔術をやっていなかったら絶対つまらないと言ってスルーしていたであろう試合がありました。
UFCファイトナイトの デ・リーダー vs アレンの試合です。
1Rの序盤から組の展開に移行し、デ・リーダーが払い腰でテイクダウンを奪うと、そこから素早くマウント、バックへ移行し4の字ロックを完成させるという、教科書のような流れでした。
かつての私であれば、この一連の動きは「マウントとれた、やったー!」「バックすげー!」という感想で終わっていたでしょう。あるいは、組み付いた時点でよそ見していたかもしれません。
しかし、柔術を始めてからは違います。
テイクダウンに至るまでの脇の差し合いで、デ・リーダーがどのようにアレンのバランスを崩していたのか。払い腰を仕掛ける前に足の運びで相手をどの位置に誘導していたのか。テイクダウン直後に、なぜアレンは一瞬の隙も作れずマウントを許してしまったのか。
それまでの微細な技術の攻防になんて注目せず、ただ流して見ていたと思うと、本当にもったいないなと思いました。
寝技の経験を持つと、これらの一本の動きに繋がる数秒間の駆け引きの全てが、勝利へ向けた決定的な要因として見えてくるのです。
【まとめ】MMA観戦の奥深さは寝技にあり
かつて、打撃こそが格闘技の正義だと信じていた私が断言します。
柔術やグラップリングは、格闘技観戦の「セカンドステージ」の扉を開けてくれます。
スタンドは爆発、グラウンドは構築。
この二つの要素が合わさって初めて、総合格闘技は総合格闘技足り得ます。
まずは道場へ足を運んでみませんか?
「打撃なし」のグラップリングなら、怪我のリスクは少なく、運動未経験でも気軽に始められます。格闘技ファンなら既に持っているフィジカルやタフネスも生かせます。
まずは見学や無料体験で構いません。一度マットの上に足を踏み入れ、実際に重圧と論理を学んでください。
そうすれば、次にあなたがMMAを観戦するとき、選手たちがグラウンドにもつれ込んでも、「膠着」ではなく、まるで全身を使ったハイレベルな知的なチェスを観戦しているように感じるはずです。
そして、そのときのMMA観戦の深みと楽しさは、あなたが知っている世界の比ではないでしょう。
UFCなどの海外の試合も楽しもう!語ろう!
選手のストーリー重視のPRIDE/RIZINもとっても大好きです。
Japanese MMAはそういう部分で楽しめるのが醍醐味なのはわかります!
一方で、UFCはストーリーもあんまりわからないしおもしろくないから観ないと言ってスルーしていませんか?
せっかくなら世界最高峰の技術の戦いであるUFCも楽しく観てみたくないですか?
みなさんといろんな寝技の攻防のおもしろさについて語り合いたいです!